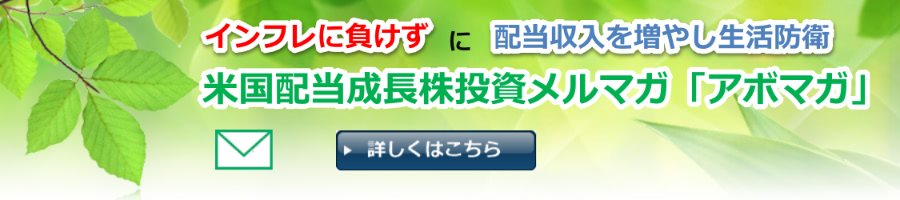1920年代のアメリカバブルから見るバブルの正当化
私たちの世の中には、ある日突然最悪な出来事が起こす可能性のあるもの(Fragileなもの)が沢山存在します。 その中でも顕著なのはバブルです。
バブルが起こる要因には必ず欲望といった人間心理が関わるものですが、それだけではなく考えるべき点があります。 それはバブルの時代に脚光を浴びた経済学者やファインナンス理論という権威のあるものによって、バブルが正当化されることです。
今回は世界恐慌を引き起こすきっかけとなった、1920年代のアメリカの歴史を簡単に振り返ります。 そしてここから学者や理論といった権威のあるものがいかに世の中を正当化していき、その結果取り返しのつかない出来事を起こすのかを見ることにしましょう。
1920年代のアメリカのバブルを正当化した3つの要素
1920年代のアメリカの景気は凄まじく、様々な経済学者や経営者から新時代と呼ばれるほどでした。 しかしこのバブルは最終的に世界恐慌を引き起こして、その後アメリカの経済が完全に回復するまでに30年近くかかりました。
1920年代のアメリカ経済は大きく分けて次の三つによって牽引されました:
- テクノロジーの発展
- 生産性の向上
- 経営の進歩
まずはテクノロジーの発展です。 代表例は何といっても車です。 既に車は発売されていましたが、発売当初は一般庶民が手を出すことができないほどの高級品でした。
しかし1920年代に車が大量生産されて、1914年には170万台だったアメリカの車の総販売台数が、1920年には810万台、1929年には2310万台になったのです。 これによって移動の手段が鉄道から車に変わる、交通手段の大転換が起こりました。
また家庭に電気が普及したのもこの時期でした。 都市圏以外の地方にも電気が普及し、1929年までにアメリカの2000万の世帯で電化されました。
しかしこの時代で一番目を引いたのは、何といってもラジオです。 最初の大衆放送メディアであり、多くの情報や流行を全アメリカ中に放送されるとあって、その娯楽性は革命的でした。
実際、1920年にはたった3つのラジオ基地局しかありませんでしたが、たった3年で500以上にまで膨れ上がっています。 またラジオ受信機の市場規模も、1922年には6000万ドルでしたが1928年には8億4000万ドル以上にまで拡大しました(6年で14倍!)。
このように1920年代のアメリカはテクノロジーが発達した時代であり、これがバブルを正当化する一つの要因とされました。 例えば経済学者のチャールズ・ダイスはこういったテクノロジーの発展を一つの理由として1920年代のアメリカ経済を「新時代」と名付けています。
1920年代のバブルを正当化した人物の代表は、エール大学の経済学者であったアービング・フィッシャーです。 彼は生産性の向上、そして経営の進歩を理由に1920年代のアメリカのバブルを正当化しました。
1920年代は企業の合併が相次いだ年でした。 反トラスト法の施行によって、銀行、鉄道、公共事業の合併が相次ぎました。 この結果、規模の経済によって生産性が向上し、これがアメリカ経済の成長、そしてバブルの正当化の大きな要因と解釈されました。
また1920年代のアメリカは経営が進歩したと言われる時代でもありました。 一つは経営者の能力の進歩です。 将来を予測したり将来を形作る能力を持った人物が今まで以上に増えたことが、企業の生産性の向上につながったと思われていました。
もう一つは経営手法の進歩です。 フィッシャー教授は"Master-charting"と呼ばれる、紙とペンを使った経営の優先順位を決める経営手法を生み出しました。 自身が発明した経営手法を含め、様々な経営手法が1920年代のバブルを牽引したと述べているのです。
こうやってテクノロジーの進歩、生産性の向上、そして経営の進歩を主な理由として、アメリカのバブルが正当化されたのです。
その他の要因
他にも1920年代のアメリカのバブルが正当化された要素があります。
例えば1913年にFRBが設立されましたが、当時はFRBによる金利の操作によって景気を完璧にコントロールできるものだと思われていました。 つまり景気が悪いときは金利を下げて経済を活況化させ、逆に景気が良くなったらバブルを防ぐために金利を上げることで市場が永遠に安定化されると思われていました。
またこの当時ブームを巻き起こした金融の理論も見逃すわけにはいきません。 1920年代に登場した、株式は投資対象としてそこまでリスクが高くないことを示した統計的な根拠を示した理論が、株式投資の大ブームを起こしたと言われています。
その代表がエドガー・スミスでしょう。 彼は1924年に著した「Common Stocks as Long-Term Investments」の中で、株式は債権よりもリスクが少なく、株式を長期保有することによって常に債権よりもリターンを出すことを歴史的な統計を利用して示したのです(ただしスミスの考え自体には一理あります)。
フィッシャー教授も、スミスの本を読んだ一般の国民たちが株式投資のリスクを理解した(つもりになった)ことがバブルを引き起こした一つの要因だと述べています。
バブルの終焉
実際に1920年代のアメリカの経済は成長しまくりました。 これによってフィッシャー教授のような経済学者は一躍有名になり、正当化されていきました。
フィッシャー教授は1929年の秋に次のような有名は発言をしました:
Stock prices have reached what looks like a permanently high plateau.
(株価は永遠の高原状態のようなところに到達したようだ)
つまり株価は今後永久に上昇し続けると発言したのです。
その3日後、株価の大暴落が起こりました。
今までフィッシャー教授の発言は正しいように思えました。 しかしたった一つのフィッシャー教授の誤りは、あらゆるものを吹っ飛ばすことになったのです。
関連ページ
- Antifragileとは何か?
- 何故Antifragileが重要か-ランダムと非線形-
- 不確実を味方につけて大きな利益を得るための3要素
- 非線形とは何か-Fragile、Robust、Antifragileを理解するために-
- Fragile、Robust、Antifragileとは(理解を深めたい人向け)
- 職業によってリターンの度合いが異なる-Antifragileをブレンドする-
- 失敗とテクノロジー-テクノロジーはTrial and errorから生まれる-
- ベーコンの線形モデルとは-何故理論あってのテクノロジーなのか-
- 偶然とテクノロジー-理論とテクノロジーの非対称性-
- ランダムだから人生が楽しくなる
- 「努力は報われる」を考える-漠然を愛する考えの提案-
- 企業の目標はオプションが多い-企業と個人の目標の置き方の差異-
- 土壌を広げて成功を待つ-Antifragile的成功への考え-
- 犠牲と利益-大きな利益を得るためには必ず犠牲が伴う-
- 犠牲と利益-列車の安全性の裏に乗客の犠牲あり-
- 失敗は大きな利益を得るための情報
- 平均は求める場所ではない-尖ったものが合わさってバランスをとっている-
- Ludic fallacyとは-現実世界をゲーム的に捉える考えの過ち-
- Ludic fallacyと教育-学校で学ぶ確率はすべてゲームの世界-
- 経済学教-Economics rationalizes us-
- Known unknownsとUnknown unknownsとは
- 1920年代のアメリカバブルから見るバブルの正当化
- 専門家とFragile-1920年代のアメリカバブルから見える教訓-
- つながりの力-独立性の有無が大人数の選択の意味を変える-
- 自分で自分の文脈をつくる-成功本には必ず文脈がある-
- 帰納の問題と食品の安全性-被害が出るまで安全かどうかはわからない-
- レーシック手術と帰納の問題
- Iatrogenesis(医原病)とは何か-医者は別の病気を生む-
- 血液を医師に抜き取られて死んだ男、ジョージ・ワシントン
- 女性特有の病気とIatrogenesis-ヒステリー&マンモグラフィー-
- スウェーデンの結核死亡率の歴史-寿命を延ばす要因は医療だけではない-
- 生存率と死亡率の違い-医療と正しく付き合うために-
- リード・タイム・バイアスとレングス・バイアスとは
- 生存率は医療界の生存にプラスに働く
- 健康基準に根拠があるとは限らない、科学的に決められたとしても
- 医師の診断を確率的に考えてみる-Base rate neglect-
- 正しさを追い求めることの罠-正しさとFragile-
- 正しさを追い求めることの罠-正しさと心理との関係-
- 一次効果と二次効果とは-何故計画は現実を過小評価するのか-
- 不安定が安定をもたらす-人工呼吸器とJensenの不等式-
- 投資の教え、安全域の原則とAntifragile
- リスクとボラティリティとの違い-ボラティリティはリスクにも利益にも変化する-